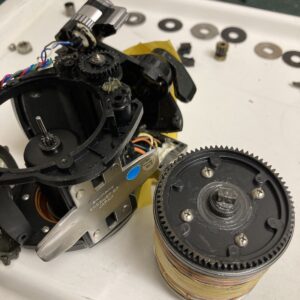タチウオ天秤仕掛け
天秤仕掛けはタチウオ針にハリス7号2mが基本です。針のチモトにビニールチューブを付けて呑み込まれても糸が切れない工夫をしています。針の結び方も丸い輪(カン)に糸を結ぶのではなく、外掛け結びでカンのすぐ下に結ぶ方もいます。ビニールチューブも付けません。これは外掛け結びで結ぶと針から真っ直ぐに糸が出るので、エサが回らないということとエサが自然にフワフワするようにするためです。切られてもいいから、まずタチウオが口を使ってくれることの方が第一だという考えです。しかし、最近私の考えはちょっと変わってきています。タチウオ針のチモト近くに2箇所か3箇所ケンが付いていて、それがエサがズリ落ちるのを防いでいます。外掛け結びをしてしまうと、ケンがあるのを有効に使えなくなってしまうからです。糸が邪魔になってケンでエサが止まらないことにもなってきてしまいます。ですので、最近はカンに直接結んでいます。
お友達から言われて、最近フラッシャーを付けています。これを使ってみたところ、かなり有効のような気がしています。当たりが以前の何も付けていない針よりかは多いと思います。
マルフジのフラッシャーを1cm幅に二つ切って、それをカンを隠すように貼り合わせます。合わせたチモトを細い木綿糸で縛るとふさふさ感が増します。縛った木綿糸にアロンをちょっと付けておけば早々は取れません。これに当然エサを付けます。今のタチウオはあまり大きくエサを動かすと追って来ないので、静かに漂っている感を出せば喰ってきます。底から5m前後のタナでじっと放っておいても喰ってくることがあります。動いていないエサを喰うのですから、はっきりとした当たりはありません。喰っているのかそうでないのかよくわからないような感じです。はっきりとした当たりを期待しているとわけがわからないまま終わってしまいます。
Instagram tadakuni744